- PDNレクチャーとは?
- Chapter1 PEG
- 1.胃瘻とは
- 2.適応と禁忌
- 2.1 適応と禁忌
- 2.2 疾患別PEG適応
- ①パーキンソン病
- ②アルツハイマー病
- ③頭頸部癌
- ④ALS
- ⑤認知症
- ⑥脳血管障害
- ⑦食道がん
- 3.造設
- ①分類
- ②Pull・Push法
- ③Introducer原法
- ④Introducer変法
- ⑤胃壁固定
- 3.2 術前術後管理
- 3.3 クリティカルパス
- 4.交換
- 4.1 カテーテルの種類と交換
- 4.2 交換手技
- 4.3 確認方法
- ①交換後の確認方法
- ②スカイブルー法
- 4.4 地域連携・パス
- 5.日常管理
- 5.1 カテーテル管理
- 5.2 スキンケア
- 6.合併症・トラブル
- 6.1 造設時
- ①出血
- ②他臓器穿刺
- ③腹膜炎
- ④肺炎
- ⑤瘻孔感染
- ⑥早期事故抜去
- 6.2 交換時
- ①腹腔内誤挿入と誤注入
- ②その他
- 6.3 カテーテル管理
- ①バンパー埋没症候群
- ②ボールバルブ症候群
- ③事故抜去
- ④胃潰瘍
- 6.4 皮膚
- ①瘻孔感染
- ②肉芽
- 7.その他経腸栄養アクセス
- 7.1 PTEG
- 7.2 その他
- ●「PEG(胃瘻)」関連製品一覧
- Chapter2 経腸栄養
- Chapter3 静脈栄養
- Chapter4 摂食・嚥下リハビリ
- PDNレクチャーご利用にあたって


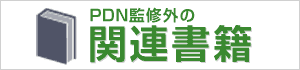
Chapter1 PEG
2.2疾患別 PEG適応①パーキンソン病
国際医療福祉大学医学部 医学教育統括センター 荻野 美恵子

2024年4月12日 改訂
① パーキンソン病(症候群)の疾患概念
パーキンソン病は高齢者になるほど多くみられる、体が徐々に思うように動かせなくなる病気です。手足のふるえ(振戦)やこわばり(固縮)、体の動きがゆっくりになる(動作緩慢)ことが特徴で、進行するとバランスを崩したときに立て直すことが下手になる(姿勢保持障害)ため、ころびやすくなります。これら運動症状のほかにも、非運動症状といわれる自律神経症状(便秘や頻尿、起立性低血圧)、うつ状態、意欲の低下、睡眠障害(レム睡眠異常、日中の過眠、レストレスレッグ症候群)などを生じます。
原因は特定できていませんが、脳の中の体をスムーズに動かす神経(中脳の黒質ドパミン神経細胞)にαシヌクレインというたんぱく質が凝集してたまってしまい、ドパミン神経細胞が減っていくことが分かっています。60歳以上では100人に一人の頻度でみられる、難病の中では比較的頻度の多い疾患で、約5%は遺伝性です。
パーキンソン病に似た症状を示すパーキンソン症候群には多系統萎縮症:MSA (multiple system atrophy)(特に黒質線条体変性症(striato-nigral degeneration:SND))、進行性核上性麻痺(progressive supranuclear palsy : PSP)、皮質基底核変性症(corticobasal degeneration:CBD)などがあります。これらの原因も不明ですが、パーキンソン病と異なり家族性発症はまれです。
② パーキンソン病(症候群)の診断
発症は60〜70歳代であり、病歴および診察所見にて疑い、鑑別診断のために頭部MRI、DATスキャン、MIBG心筋シンチグラムなどを行いますが、初期のパーキンソン症候群はパーキンソン病と鑑別が難しい場合もあります。症状はふるえ、動作緩慢、歩行障害などですが、パーキンソン病であれば抗パーキンソン病薬が症状改善に有効であり、パーキンソン症候群ではパーキンソン病ほど著効はしないので、治療への反応をみて診断を考えることもあります。
③ パーキンソン病(症候群)の治療
パーキンソン病であれば減少してしまったドパミンを補うL-dopa剤を中心とする各種の抗パーキンソン病薬による薬物療法や、リハビリテーションなどの非薬物療法が有効です。内服薬以外では脳の中に電極を埋め込む手術をして直接脳を刺激して動きをよくする脳深部刺激治療(Deep Brain stimulation :DBS)や、胃瘻を造設し腸までの管を入れることでポンプを使って持続的にL-dopa剤を注入するレボドパ・カルビドパ配合経腸用液(商品名デュオドーパ®配合経腸用液)治療などもあります。いずれも完全に治す治療ではなく、足りないものを補充する治療です。また、2018年より京都大学にてiPS細胞由来ドパミン神経前駆細胞を用いた医師主導治験も行われています。
パーキンソン症候群はパーキンソン病ほど治療薬が効かないですが、多く用いることで多少効果があることもあります。そのほかリハビリテーションをはじめとした対症療法を行います。
④ パーキンソン病(症候群)の経過
パーキンソン病は抗パーキンソン病薬の調整により、約10年は通常の生活ができる程度にコントロール可能です。しかし、進行に伴い投薬量および種類は徐々に増え、個人差はありますがおおよそ10年程度経過すると、投薬時間に相応して十分に薬の効果があるときと、不十分な時が出てくる(ウエアリングオフ)などコントロールが難しくなりますが、それでもほぼ介護なしに生活できることが多いです。その後、幻覚等の副作用がでやすくなると、投薬量の増量も難しくなり、約15~20年後には常時介護が必要な状態となります。徐々に寝たきりになり、飲み込みも下手になる(嚥下障害)ため最後は誤嚥性肺炎など合併症で亡くなることが多いですが、発症が高齢ということもあり、ほぼ天寿を全うすることになります。
また、パーキンソン病でも約半数は進行すると認知機能障害を伴うようになり、幻覚や妄想も伴いやすくなります。こうなると抗パーキンソン病薬の副作用としての幻覚や妄想も出やすくなるため、なかなか治療薬を増やすことが難しくなり、治療に難渋することになります。
中にはパーキンソン症状が出る前から認知機能障害があったり、パーキンソン症状がでてから1年以内に認知機能障害を伴うなど、運動症状よりも認知機能障害が主となる場合があります。これらは、びまん性レビー小体病と呼ばれ、パーキンソン病とは区別して認知症の一種と考えられています。
一方、パーキンソン症候群の方は病初期から治療への反応が乏しく、約10年程度で寝たきりになり、やはり嚥下障害をきたすため、誤嚥性肺炎などの合併症で亡くなることが多いです。中でも多系統萎縮症では声門開大不全を高頻度で発症し、突然死の原因となるので注意が必要です。
これら進行期では後述するように経管栄養やのどに穴をあける気管切開、人工呼吸器の使用の選択などの検討が求められることになります。
⑤ パーキンソン病(症候群)進行度と胃瘻の適応
進行すると嚥下障害を生じるために、徐々に口から食べることや薬を飲むこと(経口摂取)が難しくなり、他の病気と同様に、鼻から胃にとおす管(経鼻胃管)や胃に直接穴をあけて管を通す胃瘻などを用いて栄養を取る経管栄養といわれる方法をとるかどうか、決断を迫られることになります。パーキンソン病の進行時期を表す評価指標として5段階評価のヤールの重症度分類(表1)がありますが、嚥下障害を生じる時期はヤールの4程度以上のことが多いです。
|
パーキンソン病は、薬が効いている時間は調子よく動けるけれども、切れてしまうと動けなくなるというように、症状が薬に依存して出てくるのが特徴です。それだけ薬が効くということですが、症状が悪くなると飲み込みも悪くなるため、薬も飲めなくなってしまいます。そうなると、動きもさらに悪くなるため、さらに薬が飲めなくなるという悪循環となります。このような時に、管を使ってでも確実に薬をとることができれば、症状が改善し、そのあとは自分で薬を飲むことができるようになり、動きもよくなります。病気自体は進行するため、一時的な管の使用というわけにはいかず、ずっと使い続けることになるため、経鼻経管よりも胃瘻にしたほうが良いのではないかと胃瘻を薦められることも多いと思います。
最近胃瘻というと延命治療の一種と捉えて、拒否する方が増えてきました。しかし、パーキンソン病で服役を主な目的とした胃瘻の適応は、あくまで、できるだけ自分のことは自分でできるように、少しでも動けるようにするために必要な処置です。そう考えると胃瘻は少しでも生活の質・人生の質(QOL)をよくするための手段と捉えることができ、薬が効いてきたら経口摂取を続けるなど、もっと人生を楽しんで過ごせる方法と捉えることもできます。
胃瘻を作っても、さらに進行すると、薬が入っても以前のようには効かなくなる、もしくは副作用が問題になるという事が起こってきます。食事の経口摂取も困難になり胃瘻からの経管栄養で栄養を摂るようになります。このような状態になった時の胃瘻は、延命治療としての処置に近づいていくことになります。
パーキンソン症候群の場合は病初期から薬がそれほど効果がないため、進行期における胃瘻の造設は延命治療としての側面が強くなります。
このように、医療介入は単にどのように治療が行われるかという事だけでなく、その結果、生活がどのように変わると予測されるのか、という事を患者自身が理解して初めて判断できるものです。特にパーキンソン病のように治療薬を内服できるかどうかが大きく症状に影響する場合には誤解がないように胃瘻をとらえることが重要です。



